『外国語学習の科学』 白井恭弘 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第5章 外国語を身につけるために -- 第二言語習得論の成果をどう生かすか (その1)
ここから“第5章 「外国語を身につけるために」である。日本人が英語ができない原因として、これまで「日本語と英語の距離:言語間距離(第1章)」(ココ参照)と「動機づけの問題(第3章)」(ココ参照)の問題が説明された。そして、もう一つの要因として、「学習法の問題」がある。
本章では、第二言語習得研究の成果を確認して、さらに効果のあがる外国語学習法・教育法について検討します。(抜粋)
第5章は、5つに分け、
- その1:語学の教授法の変遷–「オーディオリンガル教授法、コミュニカティブ・アプローチ、そして誤用分析、中間言語分析—について
- その2:言語の習得順序について
- その3:インプットの重要性について
- その4:アウトプットの効力について
- その5:インプット=インターアクションモデルについて
のようにまとめるとする。今日のところは、まずは語学の教授法の変遷についてである。では、読み始めよう。
外国語教授法の変遷
外国語研究が活発になったきっかけは第二次世界大戦ごろの諜報活動の必要性からだった。外国語学習と関連の深い分野である言語学と心理学の当時の主流は、
- 「構造主義言語学」・・・「個々の言語は互いに限りなく異なりうる」というテーゼを持つ。
- 「行動主義心理学」・・・あらゆる学習は「刺激-反応」にもとづく「習慣形成」である、という学習理論。
であった。
そのため、「限りなく異なりうる」母語と外国語の対比を分析(「対象分析」)し、その違っているところを徹底的に反復練習する教授理論・「オーディオリンガル教授法」が生れた。これは、日本の英語教育にも持ち込まれて、「パターン・プラクティス」–‐‐文の変換の練習や例文やダイアローグなどの暗記による教授法–‐‐などが行われた。
しかし、一九五〇年代にノーム・チョムスキーが生成文法–‐‐すべての言語の共通性、普遍性に着目、言語の背後に隠れた構造の重要性を指摘–‐‐が発表されると、この構造主義言語学と行動主義心理学の基盤が揺らいでしまう。ここで、対象分析とオーディオリンガル教授法に時代は終わる。その後、サジェストペンディア(音楽を聞かせながら勉強する)、サイレント・ウェイ(ほとんど話さずに勉強する)などの面白い教授法が出てくるが、教授法については決定打がない状態が続いている。
誤用分析から中間言語分析
オーディオリンガル教授法が下火になった後、第二言語教育・学習に関する研究は、「第二言語習得」という分野に移る。そのきっかけは、ピット・コーダーの「誤用分析」である。それまでの第二言語学習のアプローチは、言語学・心理学理論に基づいて提唱されたが、その仮説が実際に正しいかの検証がなされていなかった。そして、それらの検証を行うと、必ずしもその仮説は支持されなかった。
そこでコーダは学習者に目を向けて「誤用分析」を行った。コーダーは、学習者の誤用を分析するという手法を用いて、学習者の習得プロセスそのものを研究対象とした。そして、この研究を境に、これまでのトップダウン的な研究から学習者の習得プロセスに注目した研究へと移行する。
しかし、学習者の誤用のみに注目していると、学習者は間違いを「回避」できるため学習の全体像は分からない、とジャクリーン・シャクターは指摘した。そのため研究は、学習者の誤りだけを見るのではなく、学習者が使う言語の全体像を見る、「中間言語分析」という方向に向かう。
まず「中間言語」とは、ラリー・セリンカーの用語で「言語習得中の学習者が自分なりに使っている第二言語、つまり学習言語」のことである。中間言語分析は、規範とあっているかを問題にするのではなく、学習者言語の「自律性」に着目し「学習者は、ターゲットとは別に学習者なりのルールをつくりあげているのだ」という観点から学習言語を見る。また、この中間言語の発達プロセスが止まってしまうことがあり、それを「化石化」という。
中間言語の形成過程について多くの研究の中で、学習者がまずターゲットとはかなりずれた文法をつくりあげ、徐々に母語話者の文法に近づいていくプロセスが観察されています。(抜粋)
一九八〇年代以降は、この中間言語のシステムがどうなっているのか、どのように発達していくのか、どのような理由でその習得パターンがみられるのか、が研究の中心課題となる。
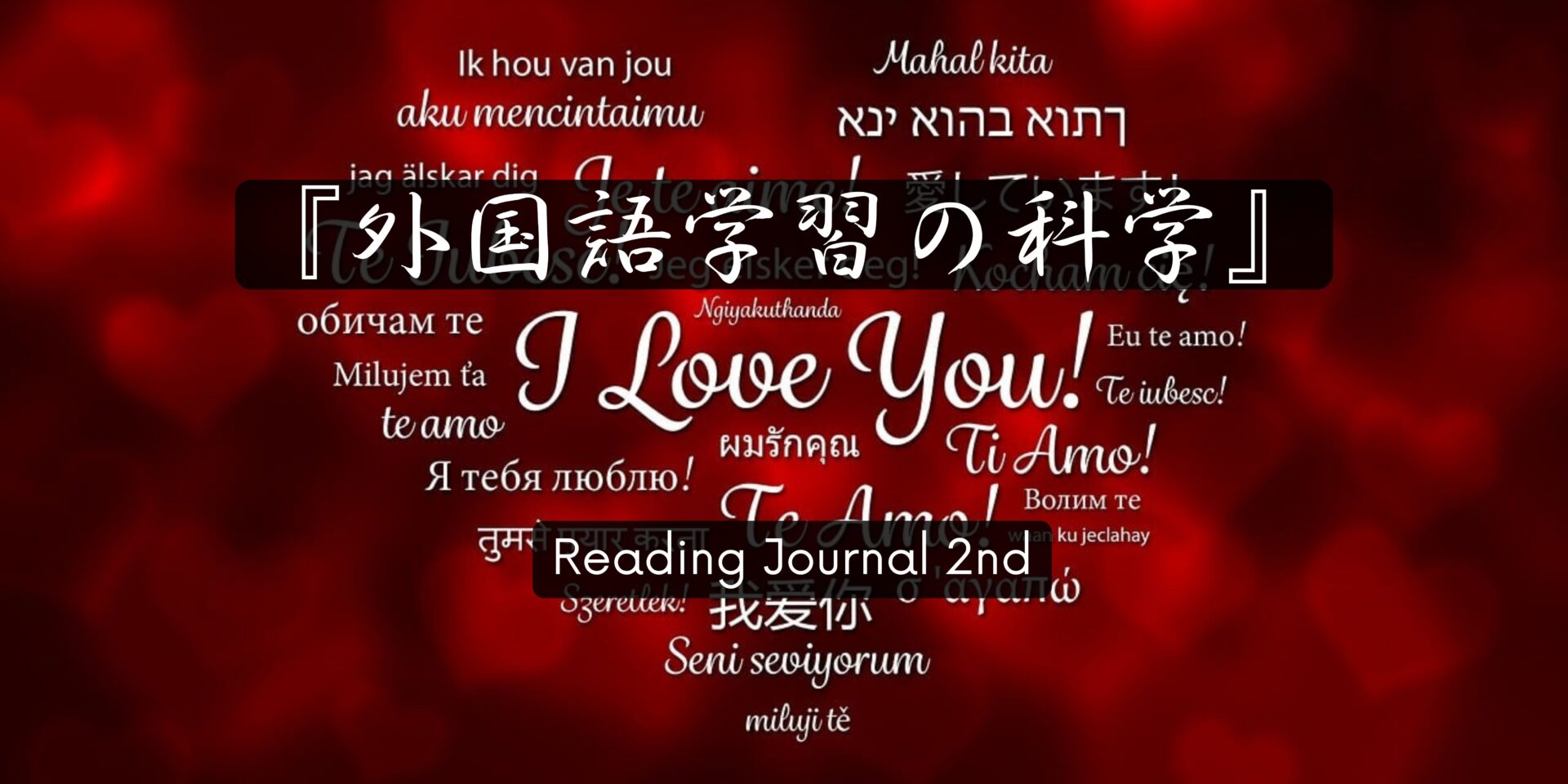


コメント