『外国語学習の科学』 白井恭弘 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第5章 外国語を身につけるために -- 第二言語習得論の成果をどう生かすか (その5)
今日のところは、第5章 「外国語を身につけるために」の“その5”である。ここでは、前回の“その4”を受けて、インプット=インターアクションモデルについて説明され、さらに今後の第二言語習得研究の課題について説明される。
コミュニカティブ・アプローチとインプット=インターアクションモデル
現在、専門家の間で効果的な外国語教授法と言われている、コミュニカティブ・アプローチは
- インプットモデル:クラシェンのインプット仮説に基づき「話すことを強制しない」方針のもとに、インプットを理解させることに最大の重点を置く教授法
- インプット=インターアクションモデル:もともと「機能主義言語学」の応用である「インターアクション仮説」が理論的基礎
がある。
マイケル・ロングが一九八〇年代に提案したインターアクション仮説は、
言語習得の根本的メカニズムとして「インプット仮説」を前提としている点では、クラシェンのインプット仮説を踏襲したものです。重要なのは、それに加えて、インターアクション(すなわち会話)に参加することにより、わからないところを聞き返したりして、「意味交渉」がおこるため、相手のインプットがより理解しやすいものになり、それで言語習得がすすむ、という考え方です。(抜粋)
実際に教える場合でも、インプット一辺倒のインプットモデルよりも、アウトプットを重視したインプット=インターアクションモデルの方が折り合いが良い。
また、ロングはその後一九九〇年代に入るとやや立場を変え、意味に焦点を置いた学習活動の中で言語形式の正しさにも注意を向けることにより、より正確な言語を習得できるとした(フォーカス・オン・フォーム)。
インプット=インターアクションモデルにもとづく会話練習を行う場合は、学習者がインプットを処理する十分な機会を保障する必要がある。そのため、日本の中学校や高校で行われている生徒同士の会話活動は、決まり文句が多く本当の意味での言語習得にはあまり寄与しない。
また、第二言語習得の場としての学校での英語教育では、コミュニカティブ活動時の言語の質に注意が必要である。言語能力には、「日常言語能力(BICS)」と「認知学習言語能力(CALP)」(ココ参照)の区別がある。しかし、中学校での活動では、「日常言語能力」のにとどまった簡単な会話が多い。日常会話ができるようになっても日本のように英語が話されていない環境では、出来ることは限られる。目指すべきは、「認知学習言語能力」である。
インプットの有効性に関する研究課題
著者はここで、第二言語習得研究の検証すべき課題を、いくつか挙げている。
インプットの質的条件
通常、外国語教師は簡単なことばで話そうとする。また、母語話者も外国人には単純化された表現(「フォーリナー・トーク」)で話す傾向がある。しかし、それは「習得に必要な言語材料を学習者から奪っていることになる」という懸念がある。また、ヘルムット・ゾブルやブレッド・エックマンは、それと逆のことをした方が良いと主張している(「投射モデル」)。
このように、インプットの重要性が基本的には共通認識になっている現在、言語項目の習得を促すインプットの質的条件(どういうインプットがより効果的なのか)について、もっと研究がなされる必要があるでしょう。(抜粋)
文法教育の限界
文法教育についても限界を意識する必要がある。ここでは、ディア・ホワイトの研究により文法教育の問題が説明されている。
いったい文法教育はどの程度効果があるのか、実際にどういうふうにやれば効果があるのか、という課題を、今後もさらに研究していくことが必要でしょう。(抜粋)
学習対象言語による違い
学習する対象の言語によっても違いがある。
母語と第二言語の関係
母語と学習対象言語の言語間距離によって、効果的学習ストラテジー(方策)が変わってくる。ここでは、ジョン・ヒョンジョンの研究を紹介している。
- 言語間距離が近い場合:母語の知識を共用できるのでインプットを大量に理解することによりかなりのレベルまで習得が進む
- 言語間距離が遠い場合:単語や文法を学習したり、例文を暗記したりするなどの意識的学習が必要。
学習対象の特徴
母語とは関係なしに学習対象言語の特色によっても効果的な学習ストラテジーが変わる。たとえば英語は文法的にはシンプルなので、かなりの部分単語の意味を把握すれば理解可能である。そのため、早い段階でコミュニケーション活動を導入できる。しかし、ロシア語のように複雑な言語の場合はそのようにはいかない。インプット中心の授業をしたり、例文や単語の語形変化の暗記をしたりするなど言語のベースとなる知識を早いうちに定着させる必要がある。
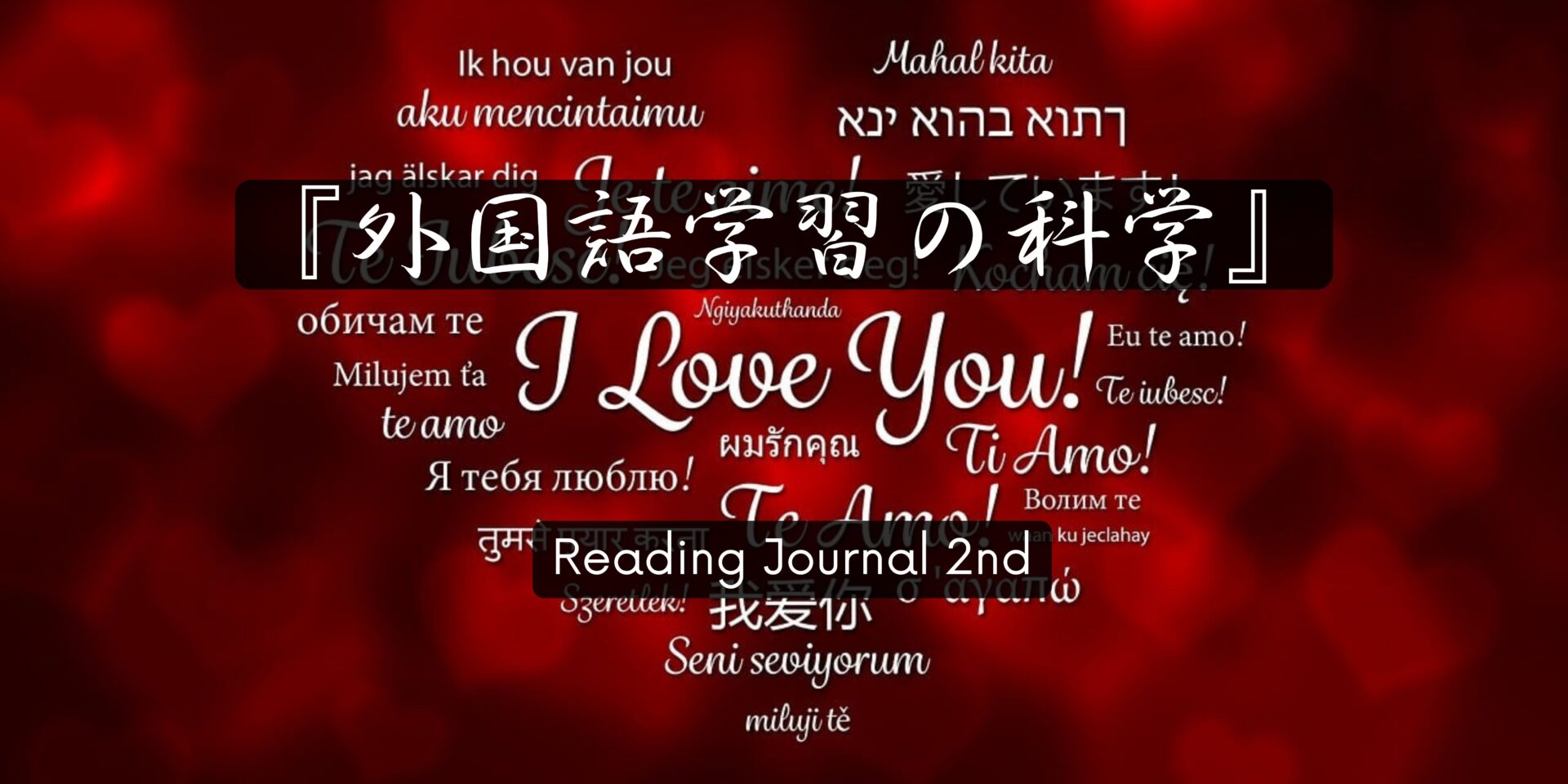


コメント