『人を助けるとはどういうことか』 エドガー・H・シャイン 著、英治出版、2009年
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
『成長を支援するということ』が読み終わった。いわゆるコーチングの本だが、なるほどと思うことが多かった。今までを振り返ると、こうしたら?ああしたらいいよ、などと相手の思いに寄り添ってないアドバイス・・・つまり支援型のコーチング・・・に始終しているように思う。ただ、どのような問いかけ・・・をすればよいか、なかなか難しい。そこで『成長を支援するということ』の「正しい問いかけ」と「間違った問いかけ」の部分(ココ)に出てきたエドガー・H・シャインの『人を助けるとはどういうことか』を読んでみようと思った。
監訳者による序文
まずは「監訳者による序文」である。冒頭で監訳者の金井壽宏は、本書について、
本書は、類い稀な「支援学」への平易な入門書である。(抜粋)
と紹介している。この本は、適切な「支援 (help)」をするために、その原理・原則を日常の具体例を活用しながら説明し、支援の基盤にある考え方を整理している。
著者のエドガー・H・シャインは、MITの名誉教授であり、組織心理学の創始者ある。経営学の分野を知る人には、「組織行動論」のレジェンドとして知られている。また、監訳者の金井は、同分野の研究者であり、弟子であるとのことである。
人は支援の達人になりたいと思っているが、実際には相手の役に立っていない「人よがりの支援」になってしまうことが多い。それは、相手(クライアント)が何を求めているかを知らずにいきなり「答え」(内容面でのアドバイス)を行ってしまうことによる。まず、クライアントが何を求めているかを知る、ともに考える過程(プロセス)が大事である。
という発想が、シャイン先生の考えと実践の土台にある。これがプロセス・コンサルテーションの考えかたであり、今日に至るまで、なんと五〇年以上も暖めてきたものだ。
最大の教訓は、クライアントのことを知らずに支援はできないということだ。(抜粋)
ここで監訳者からのメッセージが書かれている。
「この厳しい時代に支援学かよ」と思われた方は、本書を読むことによって、「こんな厳しい時代だからこそ、支援学だよ」と感じるように是非なってほしい。(抜粋)
厳しい時期だからこそ、相手の自律に役立つ実践的な支援で助け合っていきたい、というメッセージである。そしてさらにこのような支援は、もともと日本社会が得であった分野であり、そうだとすれば、このお互いに相手の自律的にする支援学は、日本にこそなじむはずであるとしている。
まえがき
本書の内容について
「監訳者による序文」につづきエドガー・H・シャインの「まえがき」がある。
支援は、すべての人間関係の基本であるが、この支援に関する感情的な動態は、ほとんど知られていない。支援をしようとしても、あっさり断られることが起こるがその原因についてあまりわかっていない。
支援者とクライアント(支援を受ける人)の間に、ある程度の「理解」と「信頼」がなければならない。支援者にとっては、いつ支援を申し入れればいいか、助けを求められ場合にどうすればよいかを知るために「理解」が必要である。同時にクライアントにとって信の問題が何かを突きとめるため、提供された支援を受け入れ実行に移すために「信頼」が必要である。
支援に関する一般理論は、(あらゆる状況での)効果的な支援と効果的でない支援との違いを説明できなければならない。
すべての人間関係は立場の問題や「状況特性」に絡んでいる。どんな人間も状況に適した行動をとりたい、立場や地位を与えられたいと思っている。そして前進するか留まるかを、自分にとっての損得などの相互関係で判断する。
支援の状況は、誰かに意識的に手を貸す。そのため、お返しを期待してしまう。お返しが感謝の言葉だけであっても、支援がうまくいけば、支援者もそれなりの地位を獲得できる。しかし、残念ながらうまくいかない場合も多く、地位を失う危険もある。必要なときに支援しなかたり、必要でも望まれてもいない支援をしようとしたり、間違った手助けをしたり、必要な支援を途中でやめたりすることが起こる。
本書は、支援を行う人間関係のダイナミクスを分析し、その関係における信頼の重要性を説明している。また、支援しようとする人は、支援が本当に受け入れられたかどうかを確かめるべきだという点や、支援を受ける人はそのプロセスが円滑に進むように行動すべきだという点も明らかにしたい。(抜粋)
本書の構成
この本は、学問的な研究書でなく、エッセイ風のスタイルで執筆されている。
この本で解説されている方法は、著者が「プロセス・コンサルテーション」と名づけた方法である。本書は学問的な論文ではなく、極めてありふれた経験を概念化するための演習であり、支援に関する理解やスキルを高め、その洞察を提供する。
最近の、支援やコーチング、コンサルティングの分析は、大半が心理学的な要素に注目しているが、本書はそれらの要素と同じくらい重要なものとして人間関係を理解するために、文化的・社会的観点から見ている。
支援は人間関係の特別なものなのでその特殊性に心を留める必要がある。その点に関して著者は、エレン・ランガーの『心はマインド —- “やわらかく”生きるために』に影響されたとしている。
最後に各章の簡単な紹介が書かれている。
- 第一章:支援のさまざまな形を取り上げ、支援の概念の広さや深さについて明らかにする。
- 第二章:経済や演劇の言葉やイメージが、あらゆる人間関係の基本を理解する上で役に立つことを明らかにする。
- 第三章:このよう概念の支援への適用とそのような関係が初めのうちはどれだけ不安定で曖昧なものかの要旨が述べられる。
- 第四章:三種類の支援の役割を述べ、支援関係はプロセス・コンサルテーションから始めるべきであると主張する。
- 第五章:控えめな問いかけを用いて支援関係を始める方法
- 第六章:控えめな問いかけの詳細な例
- 第七章、第八章:この支援モデルによって、チームワークやリーダーシップ、組織の変革マネジメントの重要な側面の理解が容易になるかについて。
- 第九章:いくつかの原則と支援しようとする人々への助言
関連図書:
リチャード・ボヤツィス、メルヴィン・L・スミス、エレン・ヴァン・オーステン(著)『成長を支援するということ』、英治出版、2024年
エレン・ランガー(著)『心はマインド —- “やわらかく”生きるために』、フォー・ユー、1989年
[目次]
監訳者による序文 [第1回前半]
まえがき [第1回後半]
1. 人を助けるとはどういうことか [第2回]
2. 経済と演劇―人間関係における究極のルール [第3回][第4回]
3. 成功する支援関係とは? [第5回][第6回][第7回]
4. 支援の種類 [第8回][第9回]
5. 控えめな問いかけ―支援関係を築き、維持するための鍵 [第10回][第11回][第12回]
6「問いかけ」を活用する [第13回][第14回]
7. チームワークの本質とは? [第15回][第16回]
8. 支援するリーダーと組織というクライアント [第17回][第18回]
9. 支援関係における7つの原則とコツ [第19回][第20回前半]
最後に [第20回後半]
解説 [第21回][第22回]
監訳者による用語解説
原注
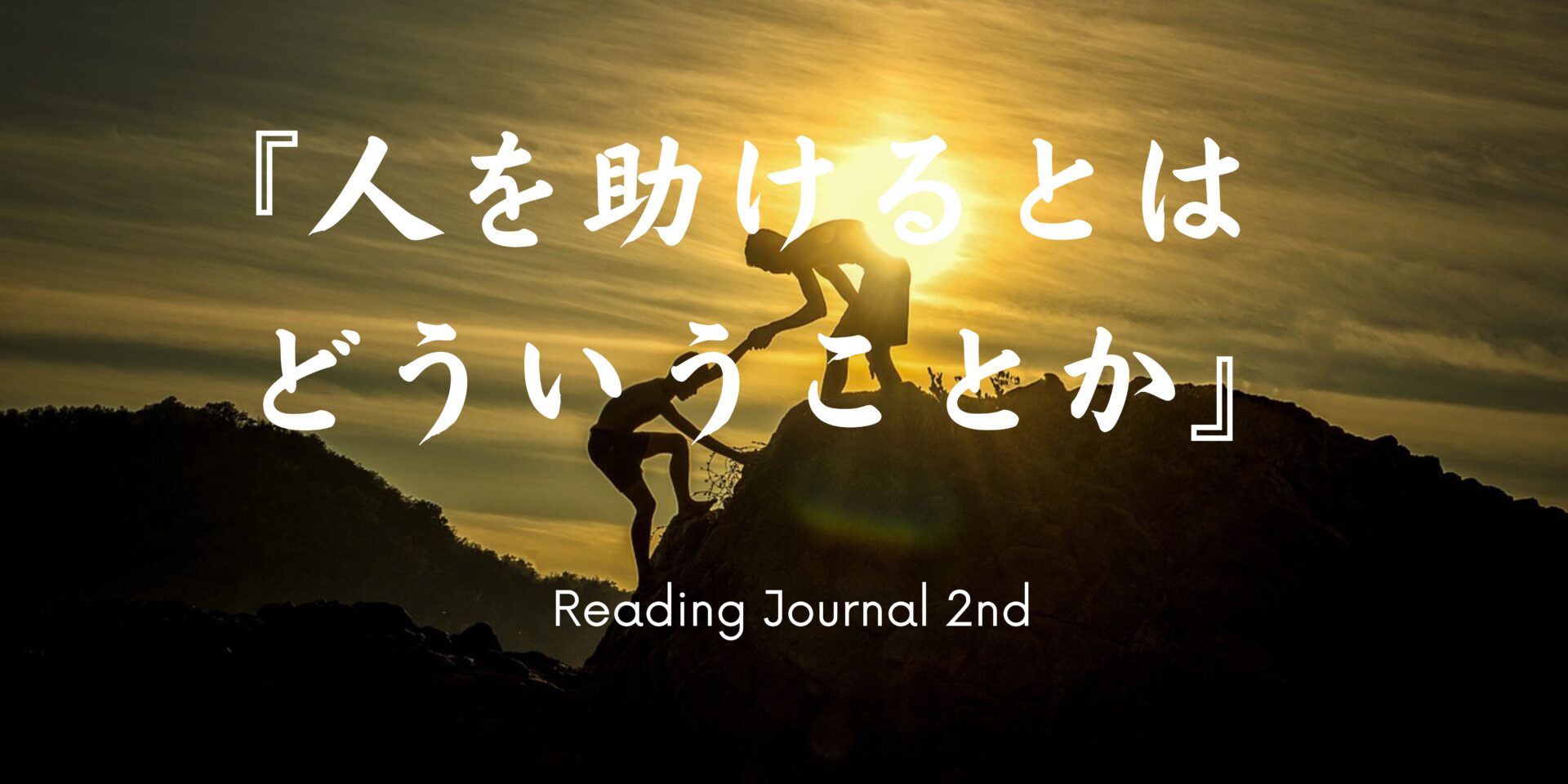


コメント