『故事成句でたどる楽しい中国史』 井波 律子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第三章 「水清ければ魚棲まず」 — 統一王朝の出現 3 前漢・後漢王朝(前半)
今日のところは「第三章 「水清ければ魚棲まず」「3 前漢・後漢王朝」の”前半“である。劉邦は項羽を破って、天下を統一した。3節は劉邦が作った漢王朝についてである。
「3 前漢・後漢王朝」は”前半“と”後半“に分け、今日のところ”前半“では、劉邦によって統一された漢王朝(前漢)について、そして”後半“では、一度滅亡した漢王朝がまた劉氏の一族、劉秀(光武帝)により再建された後の後漢についてまとめることにする。それでは読み始めよう。
「狡兎死して良狗亨られ、高鳥尽きて良弓蔵われ、敵国破て謀臣亡ぶ」韓信の最期
劉邦は、前漢王朝の初代皇帝となった。しかし本来のおおらかさを失い,しだいに猜疑心にとらわれ、残忍な性格の妻呂后の言いなりとなり、韓信、彭越などの忠臣を粛清した。韓信は逮捕されるとき「狡兎死して良狗亨られ、高鳥尽きて良弓蔵われ、敵国破て謀臣亡ぶ(すばしっこい兎が死ねば忠実な猟犬は煮て食われてしまい、高く飛ぶ鳥がいなくなれば良い弓はしまいこまれ、敵国が滅亡すれば参謀は殺されてしまう)」と嘆いた。これは范蠡の名言をふまえたものである(ココ参照)
「左袒」呂后の専横とクーデター
漢の高祖劉邦は、晩年に急速に衰え、即位後十二年で死去する。その後に実権を握ったのは、后の呂后だった。彼女は幼い皇帝を傀儡とし、一族で主要なポストを押さえ専横の限りを尽くす。
しかし呂后の死後、重臣たちがクーデターを起こし、呂氏一族を一掃した。このクーデターのとき、重臣の一人周勃が漢の将兵に向かい「呂氏の為にするものは右袒せよ。劉氏の為にするものは左袒せよ(呂氏一族に尽くす者は右肩をぬげ、劉氏一族に尽くすものは左肩をぬげ)」と呼びかけた。すると全員が左袒した。
この故事が元になり、一方に味方することを「左袒」するというようになった。
「前車の覆轍は後車の戒め」文帝の登場
呂氏が一掃された後、母の薄夫人とともに辺境で暮らしていた劉恒が皇位につき文帝となった。文帝は周勃、陳平、賈誼などの有能な臣下の意見に耳を傾ける冷静・沈着な皇帝であった。
優秀な文章家の賈誼は、しばしば上書した。後漢の班固による『漢書』「賈誼伝」には「前車の覆轍は後車の戒め(前の車がひっくりかえった跡は後の車の戒めになる)」という言葉が書かれている。
文帝は減税や減刑に配慮するなど手堅い政治を行い、社会体制を整えた。そして息子の景帝の時代になると、劉氏一族は諸王国の反乱「呉楚七国の乱」を平定し中央集権体制が確立、前漢王朝は盤石となる。
「曲学阿世」武帝の時代
文帝、景帝の時代に上昇気流に乗った前漢王朝は、第七代皇帝の武帝の時に最盛期を迎えた。武帝は、高名な儒者を招聘し、彼らの意見を聞いて儒家思想に基づいた政治機構・官僚機構を整える。
その中に、轅固生という九十余歳の老人がいた。このときともに招聘された儒者の公孫弘がこんな老人に何ができるといって、轅固生をにらみつけた。すると轅固生は、「公孫くん、曲学阿世(学問の正しい道を曲げて世間に媚びること。時流に乗るインチキ学者を指す)はいけませんぞ」といった。公孫弘は、武帝の寵愛を受けるが、とかく悪評が高かった。轅固生は一目で公孫弘を見抜いたのだった。
公孫弘のような人物もいたが武帝の儒者登用は大いに功を奏して、内政は充実した。そして、匈奴に対する対外政策は、前漢当初からの懐柔策を転換し、武力対決をした。この匈奴の撃破には、武帝の愛妻衛皇后の弟の衛青と甥の霍去病の活躍が鍵となった。
この匈奴を撃破し領土を拡大した時期が、前漢王朝のクライマックスだった。
「傾城・傾国」の美女と武帝
武帝は老齢になると衛夫人への愛も冷め、絶世の美女李夫人におぼれ、公私にわたり乱れた。
武帝に李夫人を紹介したのは、兄の李延年であった。李延年は、武帝に
「北の方に美女がいる。世に絶えてない美貌の持ち主であり。この世に一人しかいない存在である。この美人に一度見られると、男は自分の城を傾けてしまい、二度見られると自分の国を傾けてしまう。城を傾け国を傾けることの愚かしさを知らないわけではないが、こんな美女を二度とえるのは難しい」(抜粋)
という歌を披露した。そして武帝はこの美女が李延年の妹だと知ると、さっそく彼女召し寄せた。
この歌がもとになり、絶世の美女を指して「傾城・傾国」の美女というようになる。
「雁書」蘇武の手紙
武帝が李夫人との歓楽に溺れてしまうと、判断力も鈍り、対匈奴政策にも狂ってくる。そうした中、二人の将軍、蘇武と李陵が匈奴の捕虜となってしまう。この時、蘇武は降伏を拒否して捕虜として十九年を過ごし、武帝の死後、前漢の使者が身柄引き換え交渉を重ねてやっと、帰国がかなった。
この交渉の際、匈奴側は死亡したと言い張るが、前漢の使者が、蘇武からの手紙を足に結んだ雁が飛んできたから、生存は確実だと主張して、ようやく身柄が引き渡された。
この故事により、手紙やたよりを「雁書」と呼ぶようになった。
「九牛の一毛」司馬遷と『史記』
反対に李陵は、降伏した李陵を非難してその妻子を処刑した武帝のやり口に絶望して、その後の生涯を匈奴のために捧げる。
『史記』の著者司馬遷は、この李陵を弁護したため武帝の逆鱗にふれ、男性機能を失う屈辱的な宮刑に処された。
司馬遷は「世間の人は私が宮刑に処されたことなど、九牛が一毛を失う(九頭の牛の毛のなかの一本を失う)くらいにしか見えないだろ」と自嘲しながら、武帝に対する凄まじい怨念を込めて、ついに大いなる歴史書『史記』を完成させた。(抜粋)
この司馬遷の故事がもとになり、物の数にも入らないことを「九牛の一毛」というようになった。
武帝は晩年、李夫人におぼれ、その無能な兄李広利を重用したため、その後前漢王朝は凋落の坂を転がり落ちることになる。
「酒は百薬の長」王莽と前漢の滅亡
武帝の失政が目立つようになるにつれ前漢王朝は活力を失う。そして、一旦は孫の宣帝が立ち直しを手掛けたが、次の元帝、成帝と無能な皇帝が続いたため、外戚(皇后の一族)がのさばり、前漢は加速度的に衰える。
そして、前漢王朝の命脈を絶ったのは、外戚の王莽であった。彼は前漢王朝を滅ぼして、みずからの王朝新を立て皇帝となった。
王莽は即位すると『周礼』や『礼記』などの儒教の経典に合わせて行政機構を改革したり、塩・鉄・酒を専売にしたりし経済機構の改革をした。
この経済改革のキャンペーンの言葉として「酒は百薬の長(酒はどんな薬より心身にききめがある)」という言葉がある。
しかし王莽の改革は現実を無視した机上の空論であり、社会は混乱し、新王朝は「赤眉の乱」などの民衆反乱と、前漢王朝の親戚筋にあたる劉一族の反乱によりわずか十五年で滅ぼされる。
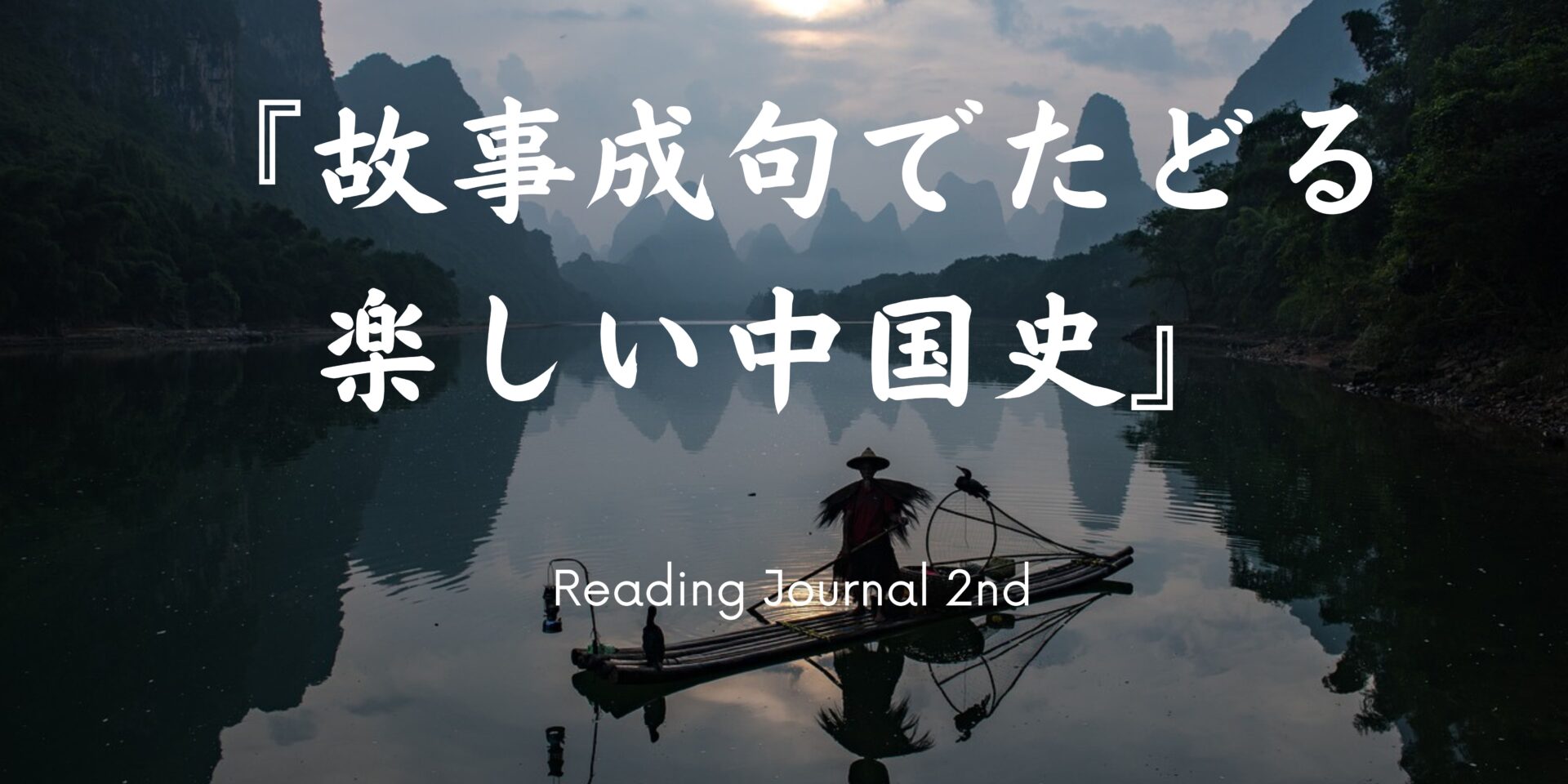

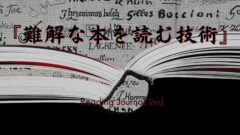
コメント