『故事成句でたどる楽しい中国史』 井波 律子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第五章 「春眠暁を覚えず」 — 大詩人のえがく世 2 士大夫文化の台頭(後半)
今日のところは「第四章 春眠暁を覚えず」「2 士大夫文化の台頭」の“後半”である。”前半“では、宗(北宋)王朝の成立と周辺諸国に不利な和平条約を結ぶことにより平和を保ったこと、そして商業が栄えた北宋の文化などが説明された。今日のところ”後半“では、徽宗皇帝の悪政により北宋が弱り、金の猛撃により北宋が滅び、江南を領土とする南宋時代の話である。南宋も金との和平条約により平和を保つが、モンゴルにおこった元により滅びてしまう。それでは、読み始めよう。
南宋の成立
金軍の猛攻が始まると徽宗は、いち早く息子の欽宗に譲位をするが二人とも靖康の変で金軍に拉致されてしまう。そしてこのときかろうじて連行を免れた康王趙構が即位し(高宗)、支配地域を江南に限った亡命政府の南宋を樹立する。
南宋は十一年ものあいだ、金軍の攻撃をかわし各地を転々としたが、ようやく首都を杭州に定めた。
「運用の妙は一心に存す」岳飛の活躍
南宋軍が金軍の猛攻をはねのけてこられたのは、ひとえに四人の名将、張俊、韓世忠、劉光世、岳飛の存在があったからである。
岳飛は「岳飛軍」と呼ばれる私兵軍団を率いて、ずば抜けた力を発揮した。岳飛が宗沢軍に加わったころ、宗沢が岳飛の軍事的才能を伸ばそうと思い、陣図を見せながら「野戦だけを好むのは万全の策ではない」と諭した。すると岳飛は「陣して後に戦うのは兵法の常なり。運用の妙は一心に存す(陣をしいてから戦うのは兵法の常識です。それをどう運用するかどうかは心ひとつにかかっています)」と答えた。
南宋と金との和平、岳飛と秦檜
金軍との戦いのなかでも和平工作がなされていた。和平交渉の南宋側の中心は、宰相の秦檜だった。この秦檜は、衡靖康の変で金側につかまり、脱走して高宗に仕えた宰相となった人で、金のスパイと言う噂が絶えなかった。
この秦檜が画策し、徹底抗戦を訴える岳飛と息子の岳雲を逮捕、処刑し、その後、金軍と和平条約を結んだ。和平条約の内容は、淮水より北を金が、南を南宋が支配する、南宋は金に臣下の礼をとる、毎年金に対して多額の賠償金を支払う、など南宋にとって屈辱的なものだった。
その後、芝居や小説のなかで、金に南宋を売った大悪人として秦檜は極端な憎まれ役となりますが、これと逆に、あくまで金軍と戦うことを主張した岳飛は漢民族の英雄として美化され、これまた極端な敬愛の対象となってゆきます。(抜粋)
「格物致知」朱子学と南宋の文化
北宋と同じように南宋も莫大な代償を払って金王朝と平和共存の道を選んだ。そしてその後、商業が発展し、文化も花開いた。
講釈を中心とする民間芸能も盛んになり、講釈師のタネ本を元にした。「話本小説」も多く書かれた。
また学術文化では、朱子(本名朱熹)が、儒学を集大成し、精緻な体系とした朱子学が確立した。
朱子学は、「四書(『論語』『孟子』『大学』『中庸』)を中心に整然と組み立てられ、雑念や欲望をとりはらって、「格物致知(物に格って知を致す)」すなわち自分以外の事物について一つ一つその理(原理)をきわめ、理についての知を獲得することを重視する。
朱子は、この「格物致知」を出発点に、修身・斉家・治国・平天下へと至ることこそ、自己を完成させ人を治める方法だと説くのです。(抜粋)
このころ詩壇も活況を呈し、陸游、范成大、楊万里などのすぐれた詩人が続々と現れた。
また南宋時代になると民間でも詩を作る人が増え、詩の大衆化が進行する。そのような風潮の中で、町や村の詩人の手本となる選集が組まれた。周弼が編纂した唐詩選集「三体詩」は、そのうちもっとも流布したものである。この「三体詩」は、江戸時代に日本でも盛んに読まれた。
「国家の不幸は詩家の幸い」金の滅亡と元好問
南宋が金と平和共存していたころ、蒙古平原にチンギス・ハン(元の太祖)が現れた。チンギス・ハンは、四方に向かって進軍し、金の首都中都を陥落させ、遠くヨーロッパまで討伐した。そしてチンギス・ハンの死後、息子のオゴタイニによって金は滅ぼされる。
金の詩人元好問は、金の滅亡に遭遇しその後元には使えず金の遺民として生涯をつらぬいた。
元好問は亡国の状況を表現した詩を数多く作っている。後世、秦の学者趙翼は、元好問の詩を評して「国家の不幸は詩人にとって幸いだ。詩を作り、世の激変を表現する段になると、その詩句はたちまち絶妙となる」といっている。
この「国家の不幸は詩家の幸い」という表現は、詩人の皮肉な運命を表現する成句として、しばしば用いられる。
「正気の歌」南宋の滅亡と文天祥
金が滅亡した後、オゴタイの死によるモンゴルの後継争いが起き、南宋はしばらく持ちこたえた。しかし、フビライがモンゴルの後継争いに勝利したあと、南宋は全面攻撃を受けついに滅亡する。
南宋にも金の元好問と同じく亡国の絶唱を残した詩人、文天祥がいた。南宋の末期に宰相となった文天祥は、首都陥落後もゲリラ戦をつづけるが、モンゴル軍に捕らえられ、獄中での降伏勧告に応じず、処刑された。
文天祥の有名な長編詩「正気の歌」は、その獄中で作られた作品である。
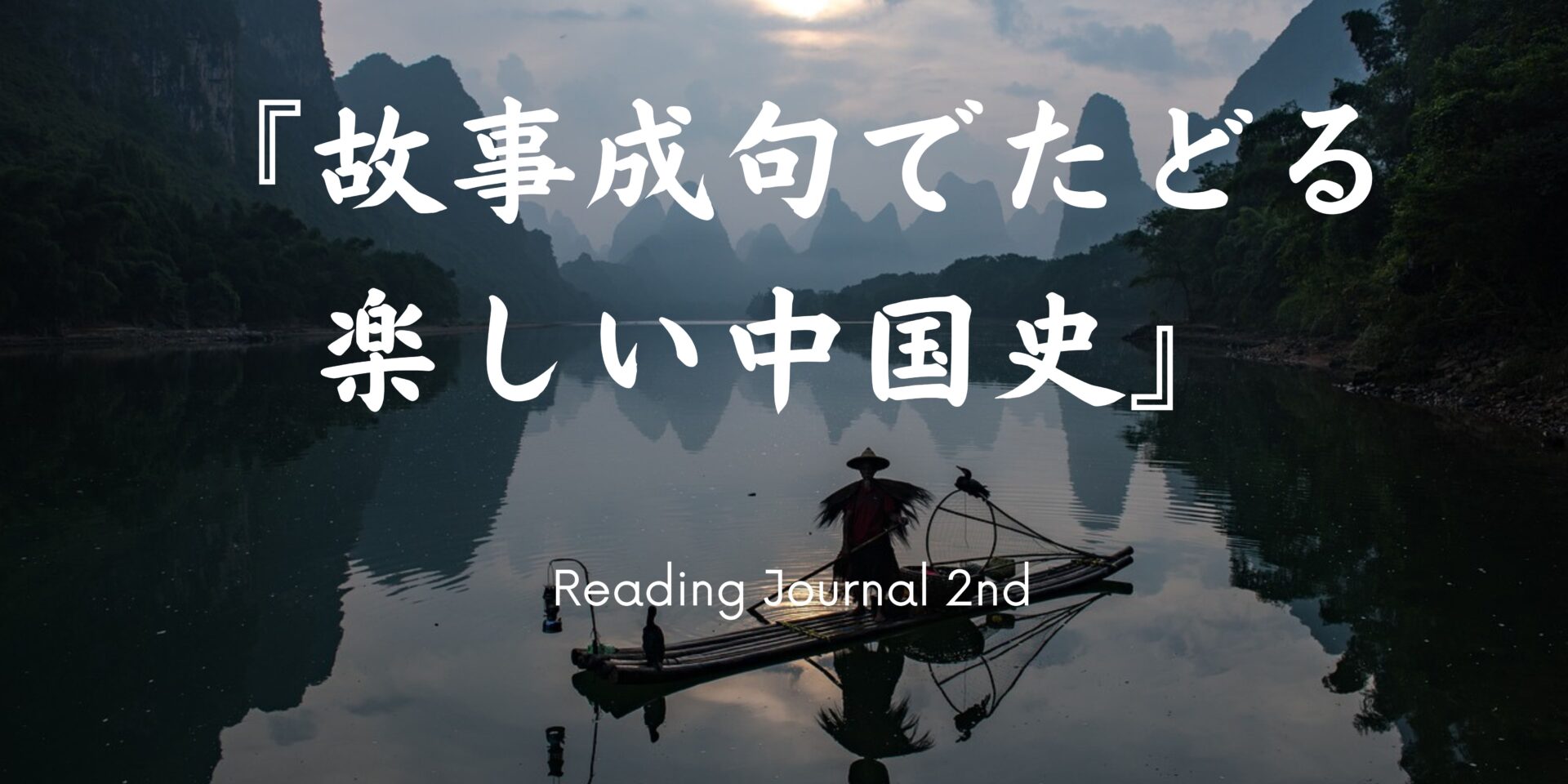


コメント