『「モディ化」するインド』湊 一樹 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第1章 新しいインド?(その1)
前回の「プロローグ」につづき、ここから本編に入る。まず第1章は、世界の国々に起こる「権威主義化」について触れたのち、モディ首相のもとで権威主義化するインドについて概説している。
第1章は、3つに分けてまとめことにする。今日のところ“その1”では、ファシズムから始まる権威主義化の歴史と特徴について解説された後、モディ首相によるインドの民主主義の後退とヒンドゥー至上主義に光を当てる。そして、”その2”では、経済、外交・安全保障の問題について、そして“その3”でモディ首相が唱える「新しいインド」、「大きな物語」についてまとめる。
権威主義化するインド
権威主義とは
著者は、一九三三年に国民社会主義ドイツ労働党(ナチ党)を率いるアドルフ・ヒトラーが首相に就任したところから話を始めた。しかし、このヒトラーは、一九二二年に「ローマ進軍」を経て政権奪取に成功したムッソリーニに比べればファシズム運動を模倣して首相の座に就いたともいえる。
そしてこのような二十世紀前半のファシスト勢力は、第二次世界大戦の敗北により幕を閉じた。
しかし、権力を獲得し、さらにそれを維持・拡大するための手法を互いに模倣し合いながら、急速に勢力を増しているという点で、近年の権威主義の台頭は二十世紀前半のファシズム運動に通じるところがある。(抜粋)
第二次世界大戦後の民主化の流れ(民主化の「第二波」)は、比較的短かったが、一九七〇年中ごろから、冷戦構造の崩壊により中・東欧諸国の民主化(第三波)が起こり民主主義体制の国が増えた。しかし二〇〇〇年代に入ると民主主義がしだいに後退し、かわって権威主義が勢いを増している。
この権威主義は、ファシズムなどの独裁とは異なり、一見すると民主主義のような体制を整え、政治指導者が発するメッセージの面でも、民主主義と区別がつきにくくなっている。
民主主義が後退し専制主義が確立する過程を、ラリー・ダイアモンドは、「専制の一二段階プログラム」と呼び、以下のような項目を列記している。
- 「反対派を正当性も愛国心もない輩だと非難するようになる」
- 「司法の独立を破壊する」
- 「司法の独立を破壊する」
- 「あらゆる公共放送を支配下に置く」
- 「インターネットの統制を強める」
また『ポピュリズムとは何か』『試される民主主義』の著書を持つヤン=ヴェルナー・ミュラーは、権威主義の体制は環境に順応できずに崩壊するという考えは幻想にすぎない。彼らは国境を越えて模倣されうると指摘している。
このような議論が念頭に置いているのは、ロシア、ベネゼーラ、トルコ、ハンガリーのような国家だが、新たにインドが注目されてきている。
インドの権威主義化
そしてすでにインドを民主主義国家と分類するのは不可能であるという認識が、専門家の中で幅広く共有されている。
「世界最大の民主主義国家」と呼ばれるインドがかつてどれほど民主的であったかについては疑問もある。
しかし、近年の急速な権威主義化は、インドがこれまでとはまったく異なる政治体制をともなう社会に生まれ変わりつつあることを意味しているのである。(抜粋)
モディが変えたインド
モディ首相の誕生と権威主義
このようなインドの権威主義化は、二〇一四年にナレンドラ・モディ首相率いるインド人民党(BJP)政権が成立して以降で、特に二〇一九年の総選挙を経て二期目に入ってからである。
著者は、その主な要因を
- 民主主義の形骸化
- ヒンドゥー至上主義の主流化
まず、民主主義の形骸化については、モディ政権は、ダイアモンドの「専制の一ニ階段プログラム」をなぞるように民主主義の枠組みを維持しながらそれを骨抜きにている。著者は、このインドの民主主義から権威主義への漸次的以降は、他の権威主義国と比べて、単なる「模倣者」ではなく、非常に勤勉で創造的な「模倣者」であるとし言っている。実際、インドが行っているSNSの統制は、ロシアや中国が行っているアクセス制限ではなく、SNSの運営会社に圧力をかけ政府に都合が良いように情報を操作するというものだが、それは、トルコ、ナイジェリア、ブラジルなどによって模倣されている。
次にヒンドゥー至上主義であるが、モディ政権が成立して以降、インドの国是というべき「世俗主義」の理念に代わって「ヒンドゥー至上主義」が政治の中心を占めるようになった。
ヒンドゥー至上主義とは、宗教的多数はであるヒンドゥー教徒が一体不可分の存在であるという前提に立ったうえで、インドを「ヒンドゥー教徒のヒンドゥー教徒によるヒンドゥー教徒のための国」にしようという、きわめて排他的で抑圧的な政治思想である。(抜粋)
アヨーディヤー「ヒンドゥー教寺院(ラーマ寺院)建立」
この「ヒンドゥー至上主義を象徴する事件」がウッタル・プラデーシュ州アヨーディヤーでの「ヒンドゥー教寺院(ラーマ寺院)建立」である。
このアヨーディヤーは、古代インドの叙事詩『ラーマヤーナ』の主人公「ラーマ」の生誕地とされ、ヒンドゥー教徒の聖地のひとつである。一方で、ムガル帝国の初代皇帝パーブルの名を冠したモスク「バーブリ・マスジット」が、十六世に建てられていた。
ヒンドゥー至上主義者は、客観的な証拠がないまま、このモスクはラーマ生誕を記念して建てられた寺院を壊してこのモスクが作られたと主張し、この場所にラーマ寺院を再建することが必要だと訴えた。
この根拠のないアヨーディヤー運動は一九八〇年代から盛り上がりを見せ、一九九二年にヒンドゥー至上主義者たちによってモスクが破壊された。そしてその後北インド中心に宗教暴動がおこり、ラーマ寺院の建設はたなざらしとなった。
しかし、モディ政権が二期目に入った二〇一九年に最高裁がモスク跡地にラーマ寺院の建設を承認する判断を示し、二〇二〇年にラーマ寺院の定礎式、二〇二四年の総選挙直前に、ラーマ神像を安置する奉献式が行われた。
このような出来事はモディ政権の一〇年で顕著となり、宗教的少数派を狙い撃ちにした差別的法律がつぎつぎと成立した。特に全人口の約一四%を占めるイスラム教徒は、その標的となり「二等市民」的立場に追いやろうとする組織的動きが顕著になってきている。
この寺院の話は、テレビのニュース番組で見た。なんかすごく乱暴な話だなと思ったが、そういうことだったんですね。(つくジー)
関連図書:
ヤン=ヴェルナー・ミュラー(著)『ポピュリズムとは何か』、岩波書店、2017年
ヤン=ヴェルナー・ミュラー(著)『試される民主主義 20世紀ヨーロッパの政治思想』(上)(下)、岩波書店、2019年
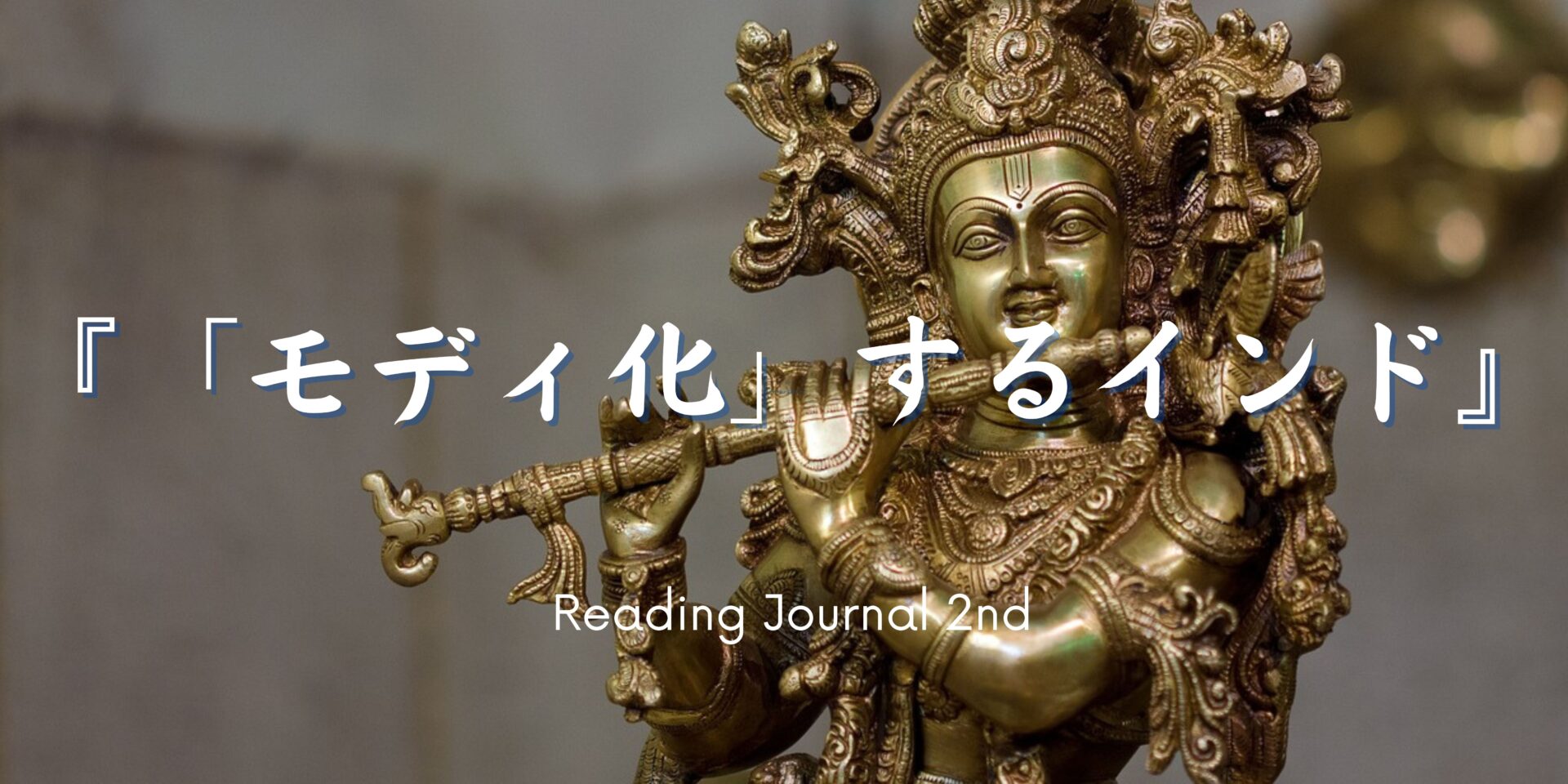


コメント