『日本語のレトリック』瀨戸賢一 著、岩波書店(岩波ジュニア新書)、2002年
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
はじめに
読書ブログを再開する(プロフを参照)ということで、これまでに辰濃和男の『文章の書き方』、『文章のみがき方』と岩渕悦太郎の『悪文』を読んできました。そこで、今度はチョット技術的な本?でも、と思って『日本語のレトリック』を買ってみました。それでは、読み始めよう!
あ!そこ!「文章全然でたらめじゃ~ん」とか言わない!だって理系ですからね!!
今日のところは、「はじめに」である。著者は、まず山を用いた言葉をあれこれ使ってレトリックというものを紹介している。「山のような宿題」、「宿題の山」にはじまり「山を越す」「山場をむかえる」「山ほどある」や「借金の山」・・・・・、それらはすべてレトリックである。
これらは、民間の言い伝えでは「ことばのちょっとした言い回し」を意味して、ありきたりな表現でなく、よりぴったりした表現、より説得力のある表現、魅力的な表現のことである。
このレトリックには、いくつかの型があり、それらをひとつひとつていねいに読むことにより諸外国の言語と同じように日本語に豊かな可能性が開けてくる。
最近の日本語ブームにより、諸外国の言葉と比べて日本語に優越感を感じたり、反対に劣等感を感じたりすることについて、著者は、それを間違った態度であるとしている。
日本語は、西洋の言語とも東洋の言語とも他の言語とも、本質的に対等な、人間の言葉である、という認識をしっかりもつべきであると考えます。(抜粋)
この表現の手段としてのレトリックは、基本的に人種や文化を越えて平等である。外国のレトリックのパタンはそのまま日本語のパタンであり、文学的な型であると同時に日常の表現の型でもある。
これで準備が整いました。ちょっとした地図も手に入れました。山頂に立って下界を見下ろすと、登山道で目にした個々のレトリックの型が、じつは私たちの思考のパタンを表している、と気づくかもしれません。この思考のパタンが日常の表現を生み、文学的な表現を生むーーー。そして、レトリックの仕組みを解きあかすことは、人間を知ることにつながる、との思いに至るかもしれません。(抜粋)
目次
はじめに [第1回]
レトリックへの誘い [第2回]
意味のレトリック
意味を転換する(意味のレトリック1)
隠喩 類似点を見つける [第3回前半]
直喩 類似点を明示する [第3回後半]
擬人法 人に見立てる [第4章前半]
共感覚法 五感を結ぶ [第4章後半]
くびき法 ひとり二役をこなす [第5回前半]
換喩 指示をずらす [第5回後半]
提喩 カテゴリーをあやつる [第6回前半]
意味を調整する(意味のレトリック2)
誇張法 度を超して伝える [第6回後半]
緩叙法 ひかえめに伝える [第7章前半]
曲言法 反意語を否定する [第7章後半]
同語反復法 意味をつなぎとめる [第8回前半]
撞着法 反意語をぶつける [第8回後半]
意味を迂回する(意味のレトリック3)
婉曲法 ズバリ言わない [第9回前半]
逆言法 言わないといって言う [第9回後半]
修辞疑問法 疑問文で叙述する [第10回前半]
含意法 意味を推測させる [第10回後半]
形のレトリック
形を加減する(形のレトリック1)
反復法 同じ形をくりかえす [第11回前半]
挿入法 ちょっと割り込む [第11回後半]
省略法 省いて伝える [第12回前半]
黙説法 黙って伝える [第12回後半]
形を工夫する(形のレトリック2)
倒置法 語順をひっくりかえす [第13回前半]
対句法 形を決める [第13回後半]
声喩 音の形で意味する [第14回前半]
構成のレトリック
仕掛けで語る(構成のレトリック1)
漸層法 しだいに盛り上げる [第14回後半]
逆説法 常識を裏返す [第15回前半]
諷喩 たとえ話で語る [第15回後半]
引用で語る(構成のレトリック2)
反語法 引用して皮肉る [第16回前半]
引喩 引用して重ねる [第16回後半]
パロディー ふざけて引用する [第17回前半]
文体模写法 文体を引用する [第17回後半]
レトリックを文章に生かす [第18回前半]
レトリック30早見表
あとがき [第18回後半]
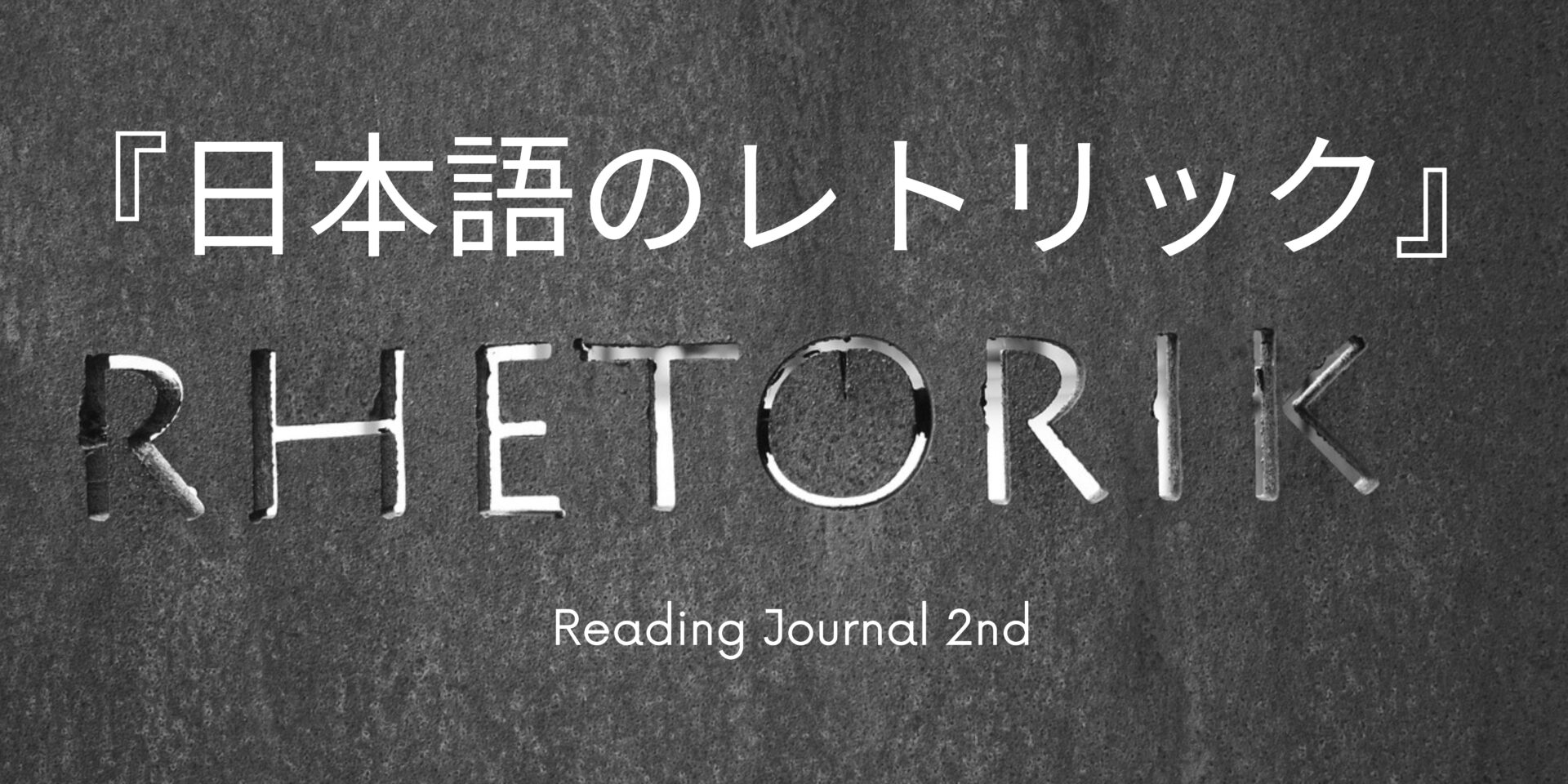


コメント