『日本語のレトリック』 瀨戸賢一 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
隠喩 類似点を見つける(意味のレトリック1 意味を転換する)
今日のところから、本編に入る。前章、“レトリックへの誘い”においてレトリックの概要の解説があった。この本では、レトリックの中の修辞部門を代表的な三〇項目をとりあげて解説していく。まずは、意味のレトリック1の「隠喩」。そして「直喩」につづく。それでは、読み始めよう。
まず、著者は安野光雅のエッセー「ものの形」(『わが谷は緑なりき』)の文章を例にあげている。
安野の文章には雪の結晶を「うつくしい花」「すばらしい宝石」と表している。これが隠喩である。
隠喩は、比喩のなかの比喩、比喩の女王である。すばり喩ます。一瞬のうちに別なるものに見たてるのです。雪は、あっというまに花や宝石と結びつく—-この電光石火の結びつきを保証するのが、似ているという感覚です。(抜粋)
この似ているは、不思議な感覚で、花や宝石と形が似ているというだけでなく、「うつくしい」「素晴らしい」という特徴も似ている。
似るためには、二つの項が必要である。喩えられる項(雪)と喩える項(花・宝石)である。典型的には、喩える項は具象的なもの、喩えられる項は抽象的なものである。(この場合は、喩えられる項(雪)も具象性を保っている)
抽象的な喩えられる項として「人生」を例にすると、人生を旅に喩えて「人生は旅」という表現ができる。するとそこに人生の道、そこを歩く旅人の姿が浮かんでくる。
また、「人生」の隠喩として「賭」とすることもできる。
「人生」を「道」と喩えるか「賭」と喩えるかは人生観の違いである。
もうおわかりでしょう。人生観とは、隠喩感です。文字どおりのことばをもたない人生について考えるには、なんらかの隠喩にたよるほかないからです。隠喩は、このとき、ことばの飾りではなく、思考そのものになります。(抜粋)
隠喩は、長い年月を経てゆっくりと沈殿していき、当初の輝きはしだいに失せて、ふつうのことばの一部になる。しかし、それは輝きを失うのではなく、底光りしているというべきでその輝きを完全に失ってはいない。また、隠喩は言葉のあらゆる層に生きていて、領域は限られない。
関連図書:安野光雅(著)『わが谷は緑なりき』(安野光雅・文集 2)、筑摩書房、1995年
直喩 類似点を明示する(意味のレトリック1 意味を転換する)
隠喩とならんで重要な比喩に直喩がある。直喩と隠喩の違いは、
- 隠喩・・・・「ヤツはスッポンだ」
- 直喩・・・・「ヤツはスッポンのようだ」
のように、直喩には「ようだ」という類似の目印がある。
しかし、隠喩と直喩の間には、中間段階があり、さらに直喩を通り越した表現もある。
- (一).ヤツはまさにスッポンだ。
- (二).ヤツはまるでスッポンのように食いついたら離れない。
- (三).ヤツは食いついたら離れない点でスッポンのようだ。
- (四).ヤツはしつこさの点で、まるでスッポンのように食いついたら離れないところがある。
(一)は隠喩ともいえるが、「まさに」が類似を合図しているともいえて、隠喩と直喩の中間点ともいえる。(二)は、どこが類似かを明示している点で直喩を越えた表現である。さらに(三)~(四)のように説明を加えた表現もできる。
一般的に直喩は説明を加えると比喩としてのパンチ力は弱まる。
ここで著者は向田邦子の「無口な手紙」(『男どき女どき』)の文章を引用して、
私は、暗に、(四)のような表現は直喩の(そして、隠喩の)いわば堕落した形態であるかのように述べました。が、それはあくまでも比喩としてのパンチ力をいったにすぎません。引用文のような上手な書き手が描けば、額にいれておきたいような表現ができあがります。そして、思うことは、隠喩と直喩(と説明つきの直喩)は連続したものだということです。(抜粋)
と言っている。
隠喩と同じように直喩にも鮮度と適切さという問題がある。遷都が良くて適切な直喩には、類似性の発見の喜びがある。
関連図書:向田邦子(著)『男どき女どき』、新潮社(新潮文庫)、1985年
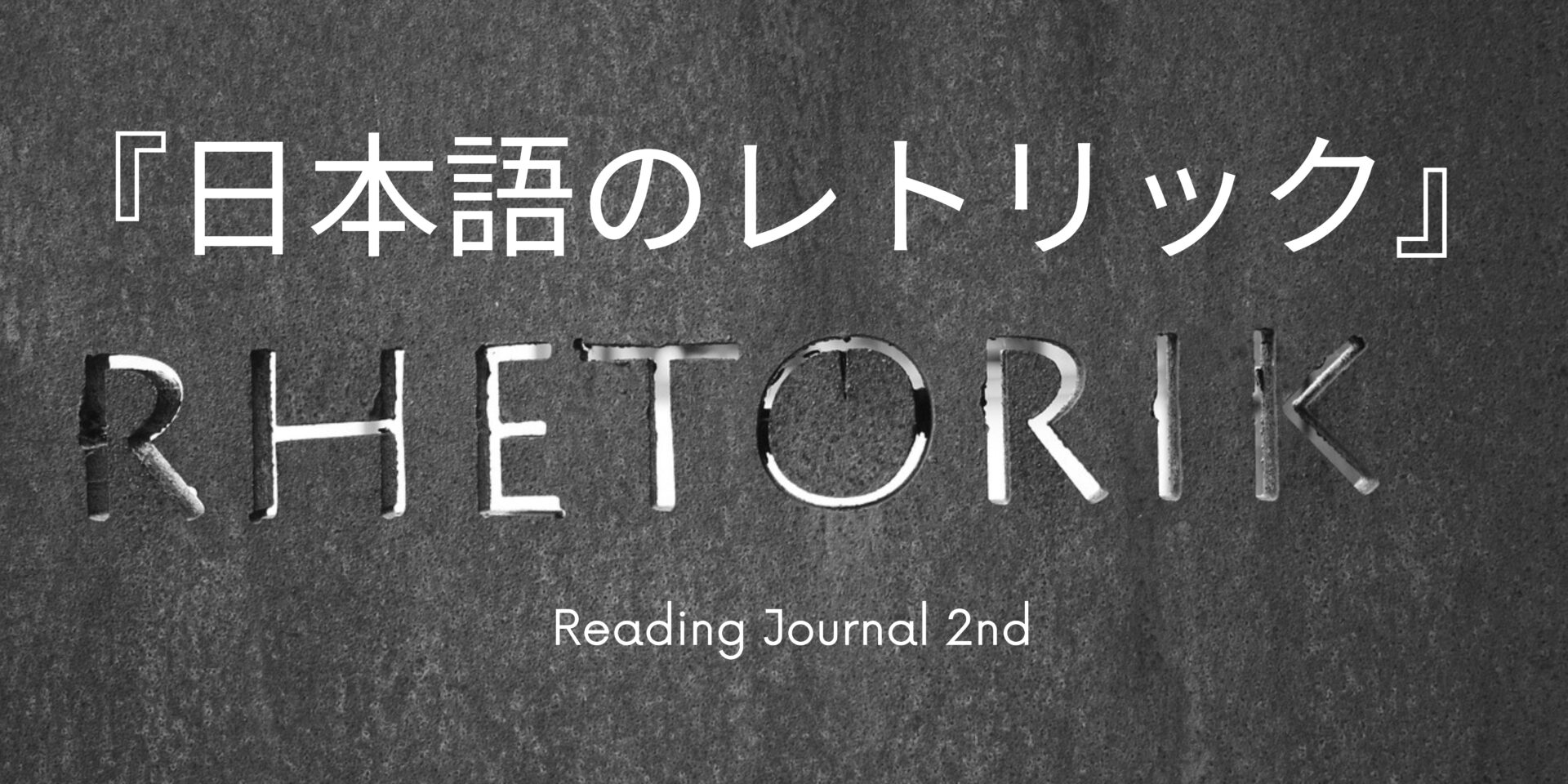


コメント