『日本語のレトリック』 瀨戸賢一 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
くびき法 ひとり二役をこなす(意味のレトリック1 意味を転換する)
「くびき法」とは、「同じ表現でその意味が異なる」というレトリックである。たとえば、野球で九回満塁のときに、ピッチャーがデッドボールを投げてしまったとき
「バッターも痛いが、ピッチャーも痛い」(抜粋)
のような表現である。ここで著者は、外山滋比古のエッセー「わたしのパブリック・スピーキング」(『はなしことば講座』)から、おかしみのあるくびき法の例を引用している。
くびき法が成り立つためには、ひとつの表現が複数の意味と対応するからである。同じ語の異なった意義を隣り合わせに使うことでくびき法の表現が出来る。
くびき法には、「服装の乱れは、心の乱れ」というような真面目なものもある。ここで、著者は、市川浩のエッセー「見知らぬ顔」(『(私さがし)と(世界さがし)』を引用している。ここでは、「身がひきしまる」と「心がひきしまる」のくびき法が使われている。著者は、この二つは一体のもののように感じると言っている。
最後に、くびき法ではない例が示される。
三面鏡をのぞいたことのない私は、新幹線の洗面所で、見知らず、身知らぬ私の外面の横顔に突然おそわれると、自分の闇に顔をつっこんだように狼狽してしまう。(抜粋)
これは音が一緒であるが意味が違うので、くびき法ではなく同音異義語である。
関連図書:市川浩(著)『(私さがし)と(世界さがし): 身体芸術論序説』、岩波書店、1989年
換喩 指示をずらす(意味のレトリック1 意味を転換する)
著者は換喩(メトニミー)を説明するために、芥川龍之介の『羅生門』(:青空文庫)を引用している。下人が羅生門で雨宿りをしている場面である。
羅生門が、朱雀大路にある以上は、この男のほかにも、雨やみする市女笠や揉烏帽子が、もう二、三人はありそうなものである。それが、この男の外には誰もいない。(抜粋)
ここで、市女笠(漆塗り中高のすげ笠)は、もとは市女(女商人)がかぶったもので、女を指す。揉烏帽子(柔らかく黒い帽子)は、それをかぶった男を表わす。
換喩(メトニミー)は、横すべりします。市女笠は、それをかぶった女とつながっていて、揉烏帽子は、同じく男とつながっています。このつながりをたよりに、指すものが横にずれているのです。(抜粋)
この換喩は隠喩のように、似ているわけではない。世界との結びつきがベースとなっている。そして、ある文脈でもっとも目立つところを表現しようとしている。
換喩にはいくつかの種類がある。
- 空間的結びつき・・・・「鍋が煮える」(入れ物で中身を表わす)、「手を貸す」(部分で全体を表わす)、「電話をとる」(全体で部分を表わす)など、いずれもまっさきに目がいったところを言葉にしている。
- 時間的結びつき・・・・「筆をとる」「筆をおく」(時間的前後関係)、「お手洗い」も手を洗うことに先立つ行為を指すので「筆をおく」の仲間である。
- 作家で作品を表わす・・・・「漱石を読む」「モーツアルトを聴く」「ピカソを観る」、大島紬を「大島」とでよんだり、スコッチウイスキーを「スコッチ」とよぶのも換喩である。
最後にまた『羅生門』からの引用に戻る。下人が、棄てられた女の遺体から髪の毛を抜いている老婆を見たときの場面である。下人の中に老婆に対する、いや悪に対する激しい憎悪がわきあがる。
下人は老婆をつき放すと、いきなり太刀の鞘を払って、白い鋼の色をその眼の前へつきつけた。(抜粋)
この場面で、突きつけられたのは「刃」でなく「白い鋼の色」となっている。それは老婆の眼に映ったもっとも目立つ特徴が「白い鋼の色」だったからである。これも換喩である。
換喩は、例文が芥川龍之介なので、なんだか文学的な感じがした。「電話をとる」とか「鍋が煮える」とかが換喩だっていわれても、なんだかなぁ~って思うけども。芥川のような表現を示されると、なるほど作家は臨場感を出すためにこういう工夫をしているのか!と納得しました。(つくジー)
関連図書:芥川龍之介(著)『羅生門/鼻/芋粥/偸盗』、岩波書店(岩波文庫)、2002年
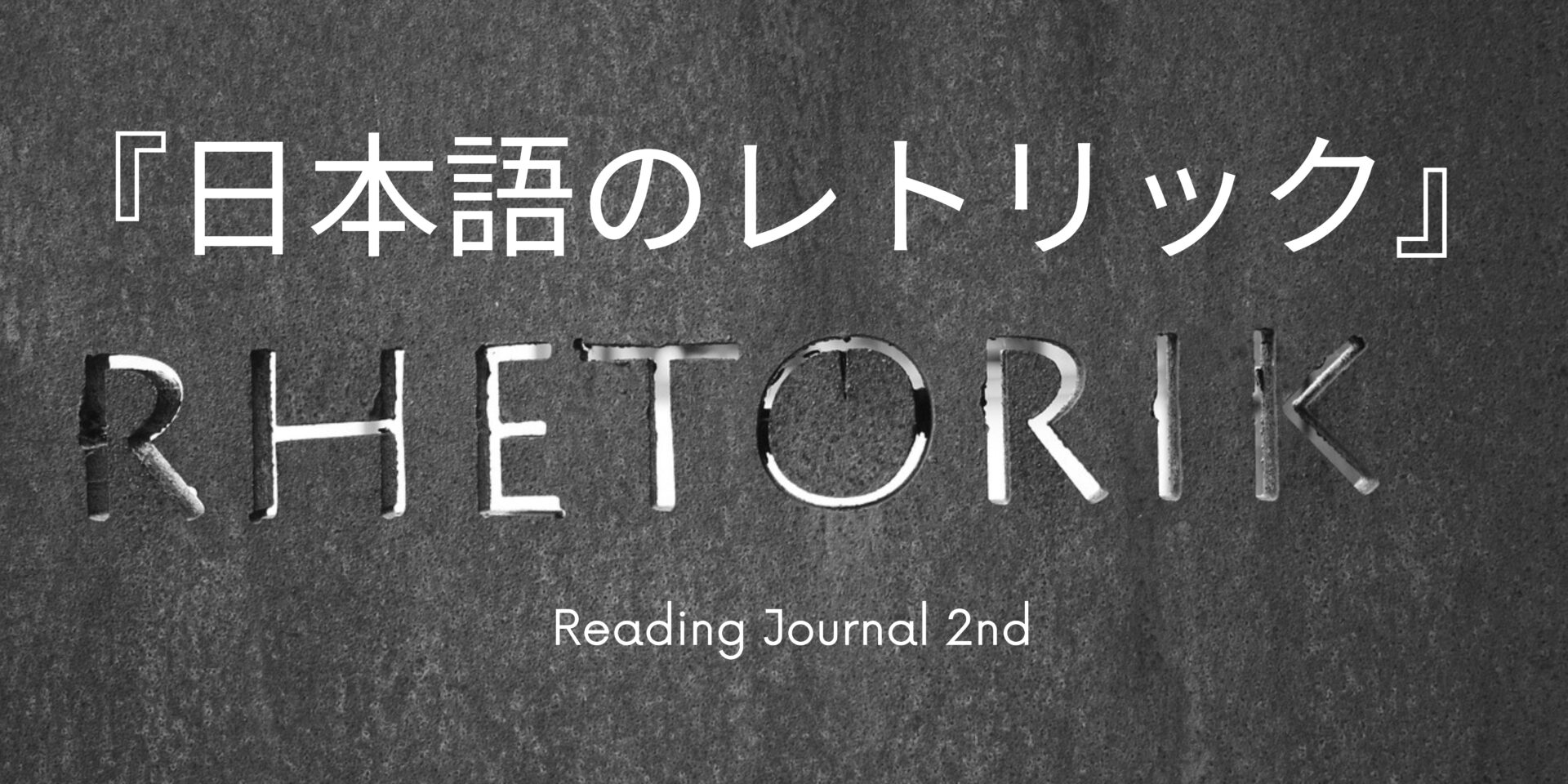


コメント