『作家の仕事部屋』 ジャン=ルイ・ド・ランビュール 編
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
やっと本文が終わった。本書の最後に「訳者あとがき」と読書猿さんの「解説 結果を約束しない様々な儀礼」がある。さて、ラストスパート!
訳者あとがき
さて、最後に簡単な「訳者あとがき」がある。ここでは、この本の成り立ちや著者について、さらにそのインタビューの仕方について簡単な説明が書いてある。
ここで著者は、このような様々な作家の仕事の場と方法について作者から引き出した答えの面白さに注目したいと言っている。
答えのひとつひとつが、いわば楽屋裏を覗く楽しみを十分に味わせてくれるだけでなく、それぞれの作家の特徴を、とりわけ作品の特性を、あるいは側面から、あるいは裏側から照らし出してくれる。視覚と聴覚による情報伝達手段が発達したとはいえ、私たちが外国の作家に接するのは圧倒的に活字を通じてであり、本書もまたそのひとつであることに違いはないのだが、バルトにせよソレルスにせよ、サガンにせよシクスーにせよ、作家がなかなか語ろうとしない《なぜ》 --- 彼らの作品がなぜあのような形態と内容をもつのか --- が、ランピュールの仕掛けによっておのずから明らかになってくる。「挿話的なものをスプリング・ボードとして利用する」という彼の意図は、みごとに成功したと言えよう。(抜粋)
解説 結果を約束しない様々な儀礼 読書猿
文庫版の最後に、読書猿さんの解説がある。解説は、在野君と平民君の対話形式で、この本の時代背景などを語っている。
まずは、この本が約五十年前に書かれてということに焦点を当てる。つまり、文庫版は二〇二三年に刊行されたが、元の本は一九七九年に中央公論社から出され、さらに原書の出版は、1978年である。
そして読書猿さんは、原書が1987年に出版されると、その年の終わりには雑誌『海』に抄訳がでて、翌年には全訳、つまりこの本が出版されたということを指摘する。そして当時は、まだフランスの知性への敬意が高かったと振り返っている。
この本は意外にも世界的に有名とう本ではなく、翻訳も日本だけである。しかし「書くことの秘密を知りたい」という欲求は尽きず、そのためこの創作の秘密を尋ねるインタビューは今でも価値があることを論じている。
しかし、作家それぞれに独自の儀礼はあるもののほとんど共通因子がない。読書猿さんはこのことを、作家それぞれの”作家儀礼“として論じ解説としている
[完了] 全27回
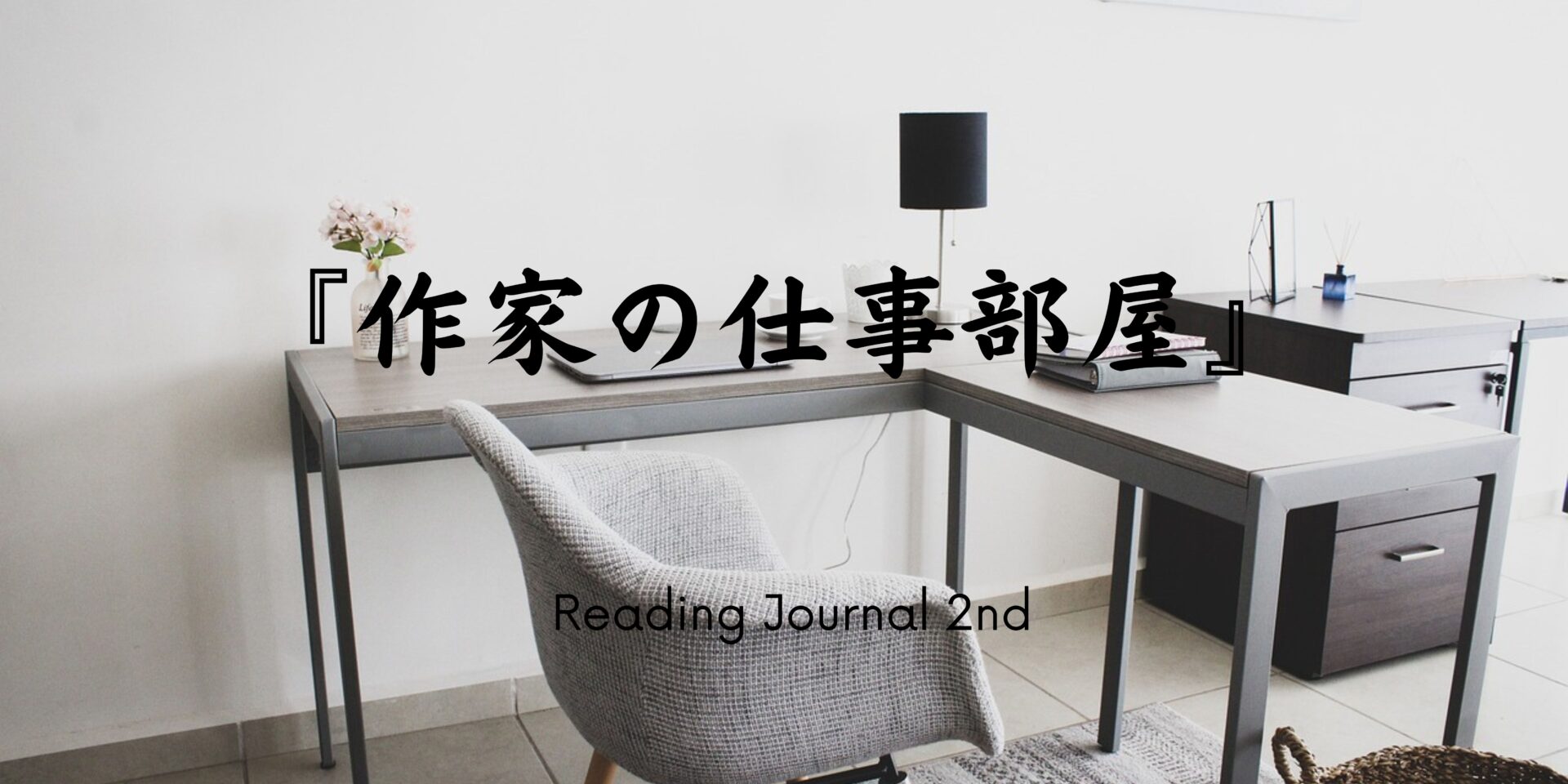


コメント