『ポピュリズムとは何か』ヤン=ヴェルナー・ミュラー 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第一章 ポピュリズムへの対処法(その4)
今日のところは「ポピュリズムへの対処法」(その4)である。前回の“その3”では、アメリカ合衆国のポピュリズムの歴史と現状について解説された。それを受けて、今回、“その4”は、ヨーロッパにおけるポピュリズムの歴史と現状についてである。それでは読み始めよう。
ポピュリズムとテクノクラシーの狭間のヨーロッパ
著者は、ヨーロッパのポピュリズムについて話を進める前に、「ナチズム(国民社会主義)」と「イタリアのファシズム」は、ポピュリズムと理解する必要があるとしている。しかし、その二つは、単なるポピュリズムでなく、「人種主義」「暴力の賛美」「急進的な指導原理」などのポピュリズム自体として必然的でない要素を含んでいた。
ヨーロッパは、一九三〇年代と四〇年代における全体主義の反省から、「戦後の政治思想と政治制度は、反全体主義」となった。そして、政治指導者も全体主義的な過去へ回帰しないような秩序を構築した。
政治指導者の全体主義的過去のイメージは、「無制限の政治ダイナミズム」「解き放たれた大衆」「制約ない政治主体」のようなものである。つまり、純粋なドイツ人からなる民族共同体やスターリン憲法に定められた「ソ連人民」などである。
結果として、戦後ヨーロッパの政治発展の全体的方向性は、(抑制と均衡、あるいは混合政体という意味における)権力の分散と、憲法裁判所のような非選出制度、あるいは選挙のアカウンタビリティを免れた制度への権限付与であり、それぞれ全てが民主主義自体の強化という名のもとで進められた。(抜粋)
このような制度には、ヨーロッパのエリートたちの二十世紀中葉の政治的崩壊を招いた教訓があった。つまり、人権主義の理想や議会主権への不信感があった。
そのため、戦後ヨーロッパの議会は意図的に弱められ、選挙のアカウンタビリティを問われない制度(憲法裁判所など)に、個人の諸権利の擁護、民主主義全体を守護する任務を負わせた。
端的に言えば、抑制なき人民主義、あるいは無制約な議会主権(かつてドイツの憲法学者が「議会絶対主義」と呼んだもの)への不信が、いわゆる戦後ヨーロッパ政治のDNAに組み込まれたのである。(抜粋)
このような「抑制された民主主義」は、20世紀の終わりの三分の一期に独裁を断ち切り、自由民主主義に転じた諸国で、ほぼ例外なく採用された。
ヨーロッパの統合(EUの設立)もこの人民主義を抑制する包括的な試みの一部である。つまり国家的抑制に超国家的な抑制を加え、自由民主主義的なコミットメントを「ロック・イン」する試みである。
著者は、ここで要点として、ヨーロッパのような「人民主義への不信に基づいて築かれた政治体制(反全体主義、反ポピュリズム)」は、「人民の参加を最小限に抑えるようなシステムに反対するし、人民全体の名のもとに語る政治的アクター」に脆弱であると言っている。
なぜならば、ポピュリズムは、実際には人民の政治参加の拡大求めていないが、そのような要求を掲げる運動に似ているため、戦後のヨーロッパのような「人民」を政治から遠ざける考え方に基づいているという理由で、いくらかの正当性をポピュリズムに与えてしまうからである。
ここで著者は、一九七〇年半ば以降にポピュリズム的アクターに対して、ヨーロッパが脆弱になったのは、「福祉国家の縮小」「移民問題」近年は特に「ユーロ危機」をあげている。
現在のポピュリズムの興隆を理解するためにはユーロ危機が重要である。しかし、危機自体はポピュリズムを生み出すことはない。問題なのはテクノクラシーによる支配である。
奇妙なかたちで、テクノクラシーとポピュリズムは合わせ鏡の関係にある。テクノクラシーは、正しい政策的解決法はただひとつだと考える。他方ポピュリズムは、唯一の真正な人民の意志が存在すると主張する。(抜粋)
テクノクラートもポピュリストも民主主義的な議論は必要ないと考え、ある意味、両者は奇妙なほど非政治的になっている。両者はそれぞれ唯一の正しい政策的解決法が存在し、唯一の真正な人民意思が存在すると考えている。
この類似点に気がつくと
- ポピュリスト政権やポピュリスト運動
- ポピュリストに似ているアクター
の区別がつく。
まず、ポピュリストとしては、フィンランドの「真のフィン人」があげられる。彼らはEUを批判するからではなく、真のフィン人を排他的に代表していると主張するからポピュリストである。また、イタリアのペッペ・グリッロは、彼の運動に議席の100%を求め、究極的にはグリッリーニが純粋なイタリア人民であるとしているからである。
一方、エリートを批判しても「全体に代わりうる一部」というロジックを用いない政治アクターはポピュリストから区別することが出来る。このようなアクターをポピュリストと区別することは、現在のヨーロッパでの重要な課題である。実際に彼らは「われわれが、それもわれわれのみが人民である」と主張せず、むしろ「われわれもまた人民だ」と主張するのである。
ここで著者は、リバタリアン(自由至上主義)に対抗するためにポピュリズム的手法をとる左翼の戦略について考察している。ここで問題なのは、リバタリアンへの批判ではなく、政治的紛争を「人民」と事実上に支配者である「市場の民」の間の争いとしていることである。このような図式は、実際に「人民」を動員することはなさそうだが、真にポピュリスト的な政治概念を問題に持ち込む可能性はある。
そのため、特定の「左翼ポピュリズム」を希求することは、無駄であるか危険である。つまり、左翼のオルタナティブ(代わりになるもの)や、社会民主主義の最発明を提示するならば無駄である。しかし、左翼ポピュリズムが本書の定義した意味でのポピュリズムを意味するならばそれは危険である。
では、オルタナティブは何であるか、それは「富裕層、権力者」のシステムから離脱させず、「排除されている人々」を参加させるアプローチである。これには新しい社会契約が必要である。このような仕組みへの支持は財政的な正確さだけでなく、公正へのアピールが必要である。また、これには新しい調停に権限を与えるメカニズムが必要で、それは大連立の形で実現するかもしれないし、アイスランドやアイルランドが試みている立法的調停を正式に再交渉するというものも考えられる。
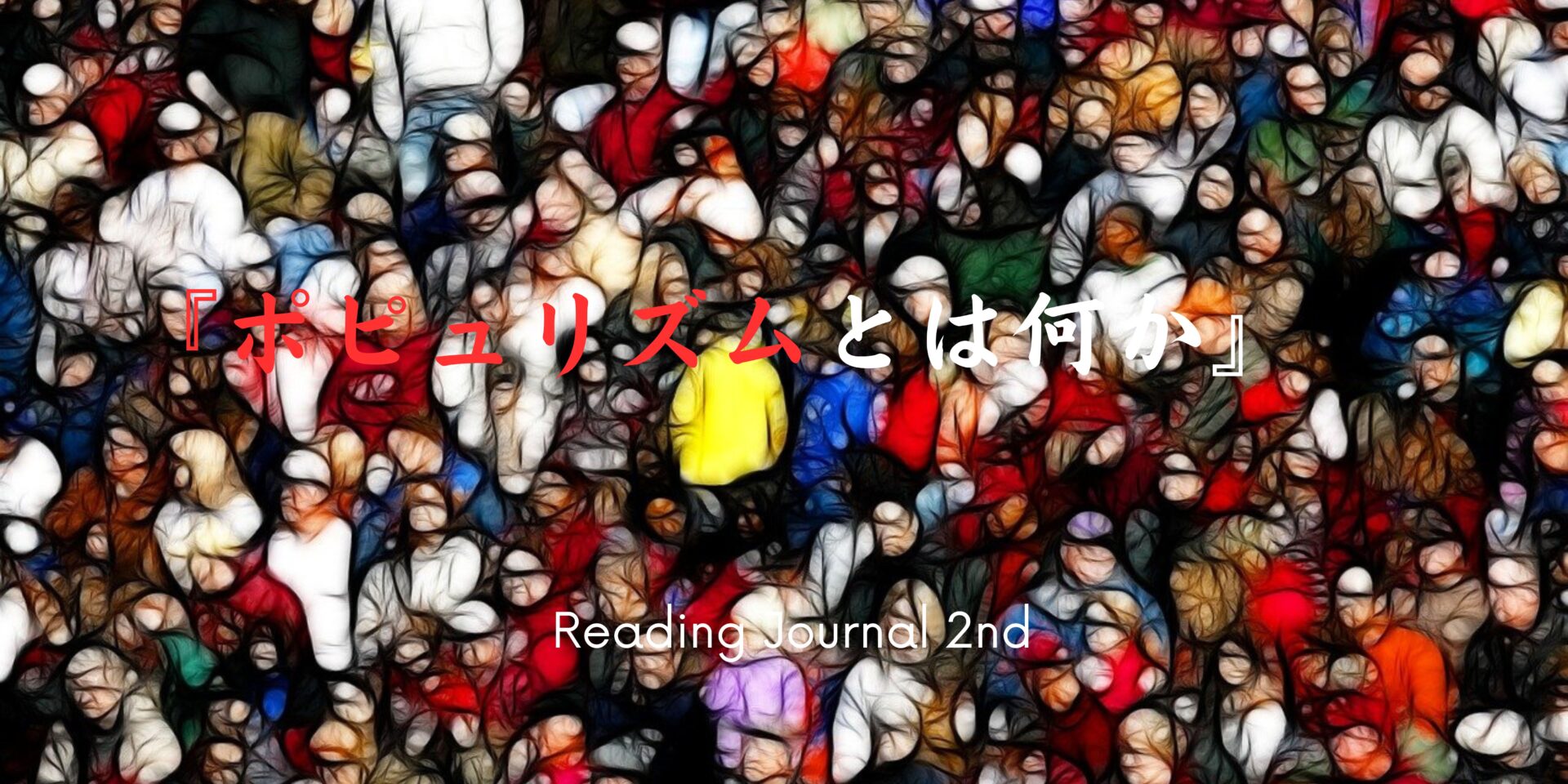
-1-120x68.jpg)

コメント