『難解な本を読む技術』 高田 明典 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第1章 基本的な考え方(前半)
「はじめに」が終わって、今日から「第1章 基本的な考え方」である。この章では『読書の技術』にまつわる基本的なことが取り扱われる。ここでは、読書で大切な「わかる」ということを説明し、「わかる」ために重要なことについて解説されている。
第1章は、前半と後半の二回に分けてまとめることにする。それでは読み始めよう。
読書とは、自分以外の誰かが書いた書籍の内容を頭の中に吸収するという作業である。 またそれは、単に吸収するだけでなく、他人の思考を自分の中に移植する作業であるともいえます。(抜粋)
つまり、読書で重要なのは「わかる」ということである。そして、この「わかる」という作業のために、「本のパターンを知ること」が必要である。また、読者の読み方として「同化読み」と「批判読み」の二種類がある。
「わかる」ということ
「わかる」という意味は、「そこに書かれている概念を使うことができる」ということである。
そのためには、まずその書物の取り扱う範囲、「問題」について知ることが重要である。著名な思想家や科学者の中には、何冊もの本を著していて、その「問題」は共通していたり、重複して居たりするため、最小限のことしか書かない場合がある。そのような場合は、他の書物を紐解くか、解説本や入門書によって、著者の問題意識や目的を知る必要がある。
翻訳の問題
ここで著者は、この本では原則として思想系翻訳書を読解するとして、翻訳の問題について触れている。
よく「翻訳が悪い」という言われることがあるが、
基本的には翻訳の問題は、それほど気にする必要はないと言えます。(抜粋)
名著と呼ばれるものはそれ相応の翻訳者が担当するため、総じてそれほど悪いものではない。また、翻訳が良かったからと言って、それで理解が容易になるわけでもない。
また、個人的な経験としながら、「翻訳が悪い」と言われる本の原著をあたっても理解に差ができることはほとんどないとし、教養としてその思想を理解したいならば翻訳でほとんど問題はないと言っている。
「閉じている本」と「開いている本」
ここから、本の類型の話に移行し、「開いている本」と「閉じている本」について説明している。
「開いている本」
「開いている本」とは、「著者が自らの考えを少なからず隠蔽しているタイプの本」である。これは読者への「問いかけ」であり、もしくは「自己決定せよ」という命令であったりする。
このような本を読んで理解するためには、特殊は技術が必要となる(詳しくは後述)。このような本を読んでいると私たちは、イライラする感覚を持つ。著者の意見が入らないため、「で、何なの?」という印象を持つ。
つまり、その「で、何なの?」という問いに対しての答えを、読者自ら創出することを想定して書かれている本が「開いている本」です。(抜粋)
「閉じている本」
「閉じている本」は「ある結論に向って着々と論を構築する本」である。そのため、ある程度まで受動的な態度で読み進めることができる。
「外部参照」が必要な本
「外部参照」が必要な本とは、その本で用いられている概念や用語の意味を理解するために、その本以外で説明されている知識が必要となる本である。これは本の性質で決まるのではなく、その本と読者との関係で決まる。
著者はある程度「読者像」を想定しているため、その想定した読者像のレベルと自分のレベルによって「外部参照」が必要か決まる。
換言するならば、読者が自分の現在のレベルを知り、外部参照が必要であるか否かを判断する必要があるということです。(抜粋)
注意しなければいけないのが、専門用語でも、一般的な文脈で勝手に理解してしまうことが可能であるということである。しかしその場合は、その後の文章がまったく理解できないということになってしまう。
研究者として(まともな)訓練を受けてきた人間は、そのような概念を「なんとなくの理解」のまま読み進めることはしません。そのような態度が、本当の理解を妨げることを知っているからです。(抜粋)
ここの「開いている本」と言うのを読んで『旧約聖書』の「ヨブ記」は、ようは究極の開いている本だってことだと思う。
たび重なる不幸に襲われ「なぜ、自分がこういう目に遭うのか」と神に問うヨブに対して、神あなたは「勇者らしく腰に帯を締めよ。あなたに尋ねる、私に答えてみよ。」と逆に問うばかりだった。
前に、読んだ小友聡の『それでも生きる 旧約聖書「コヘレトの言葉」』と同じく若松英輔と小友聡の『すべてには時がある 旧約聖書「コヘレトの言葉」をめぐる対話』でヨブ記が取り上げられていた(ココとココ参照)。
神に問い続けるヨブに、逆に神を問う。これを「問いの逆転」という解釈で理解していたと思う。また、同様な考えにヴィクトール・E・フランクルの「問いのコペルニクス的転回」があるってことで、なかなか深い意味があった。(つくジー)
関連図書:
小友 聡 (著)『それでも生きる 旧約聖書「コヘレトの言葉」』、NHK出版(NHKこころの時代)、2020年
若松 英輔、小友 聡(著)『すべてには時がある 旧約聖書「コヘレトの言葉」をめぐる対話』NHK出版(別冊NHKこころの時代宗教・人生)、2021年
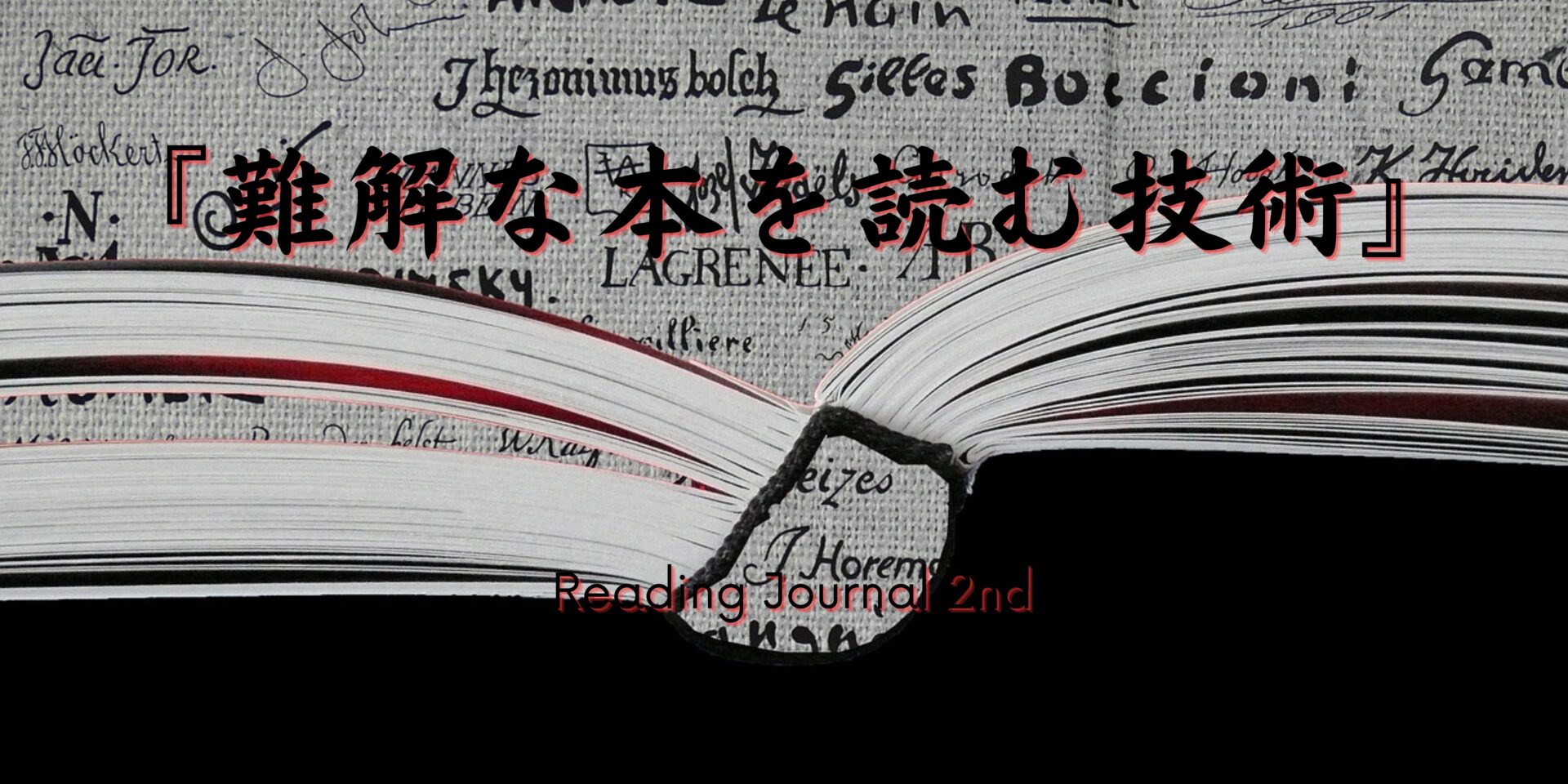


コメント